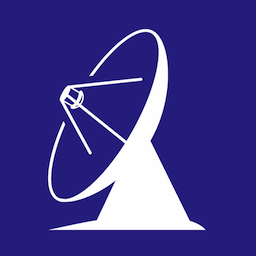2025年秋
- 東京農工大学 工学部(総合型選抜)
2024年
1人
- 上智大学 理工学部
- 電気通信大学
- 東京理科大学 創域理工学部、先進工学部
- 明治大学 理工学部
2022年秋
- 防衛大学校 理工学専攻(推薦)
2021年冬〜2022年春
高校受験 2人
- 県立浦和高校
- 開智高校 Sコース
- 川越東高校 理数コース
- 成立学園高校 スーパー特進コース
大学受験 2人
- 京都大学理学部特色入試2次選考のうち数学試験に合格
- 日本大学 理工学部
2020年冬〜2021年春
3人
- 北里大学 獣医学科(公募推薦)
- 慶應義塾大学 薬科学科
- 中央大学 理工学部
- 東京薬科大学 薬学部
- 明治大学 理工学部
- 日本学生科学賞 長野県審査通過 長野県教育委員会賞受賞 電気部分の指導
2020年春
- 慶應義塾大学 理工学部(内部進学)
- 東京都立産業技術高専
- 海城中学校、武蔵中学校 他(小6夏まで指導)
2019年
3人
- 自治医科大学 医学部医学科
- 一次試験に合格 東北医科薬科大学 医学部医学科
- 日本大学 松戸歯学部
- 日本歯科大学 新潟生命歯学部
- 東京慈恵会医科大学 看護学科、日本赤十字看護大学 看護学部(高3夏まで指導)
2018年秋、冬
- 帝京大学 看護学科(AO入試)
- 秀明中学校
2018年春
大学受験 1人
- 岩手医科大学 薬学部
- 城西大学 薬学部
- 帝京大学 理工学部
高校受験 3人
- 大宮開成高校 特進選抜先進コース
- 川越女子高校
- 埼玉栄高校 αコース、特進コース
- 昌平高校 T特選クラス
2017年
- 城西川越中学校
2016年
- 星野高校 共学部 理数選抜コース
- 数学検定 3級(中学2年生が受験)